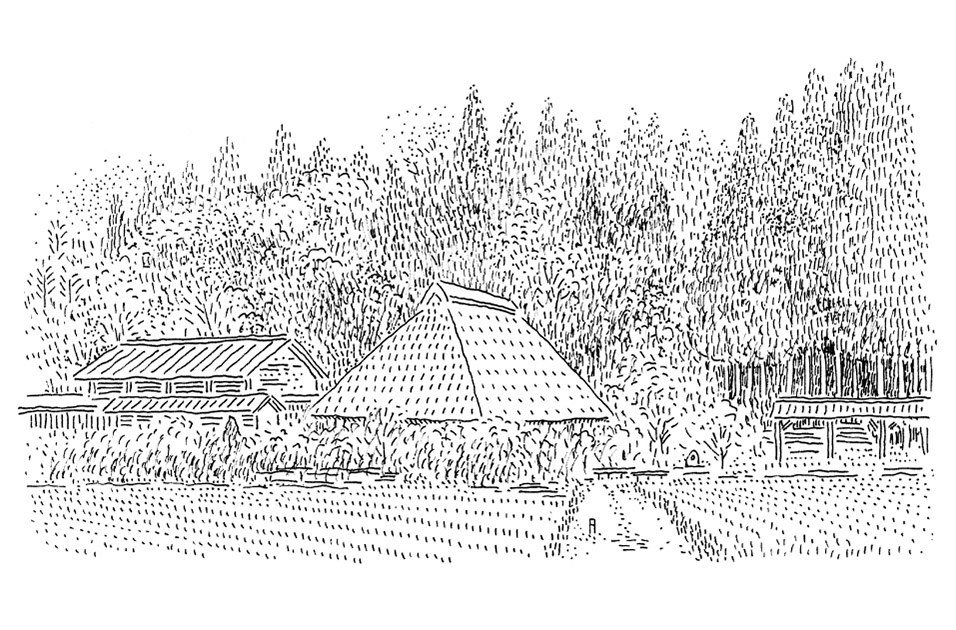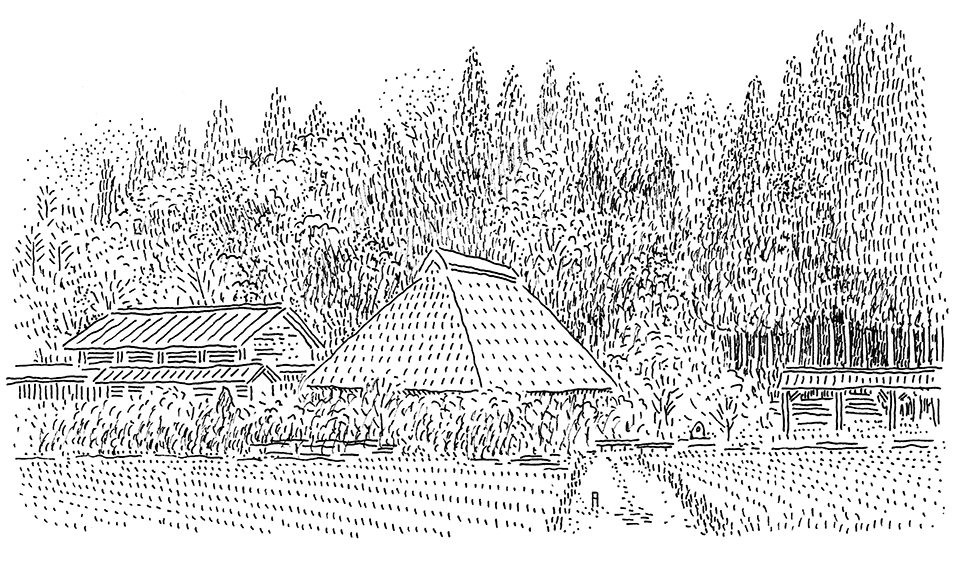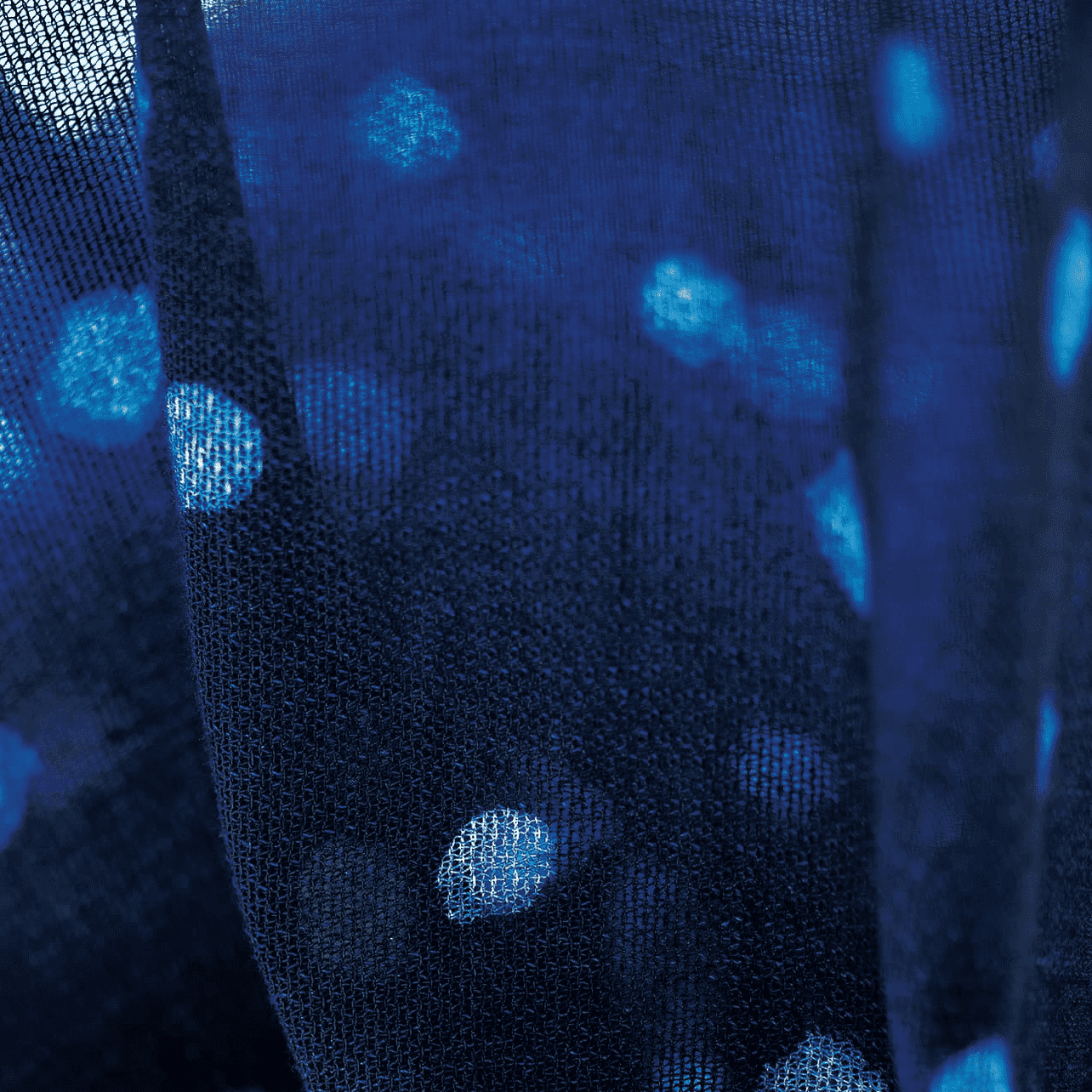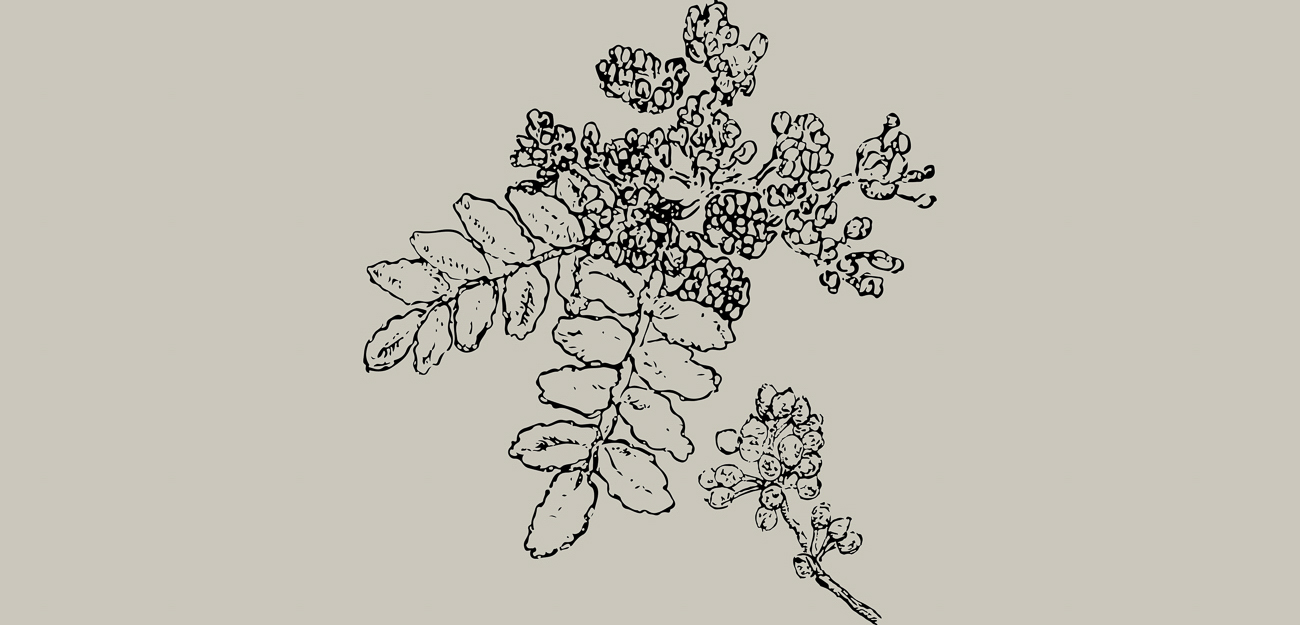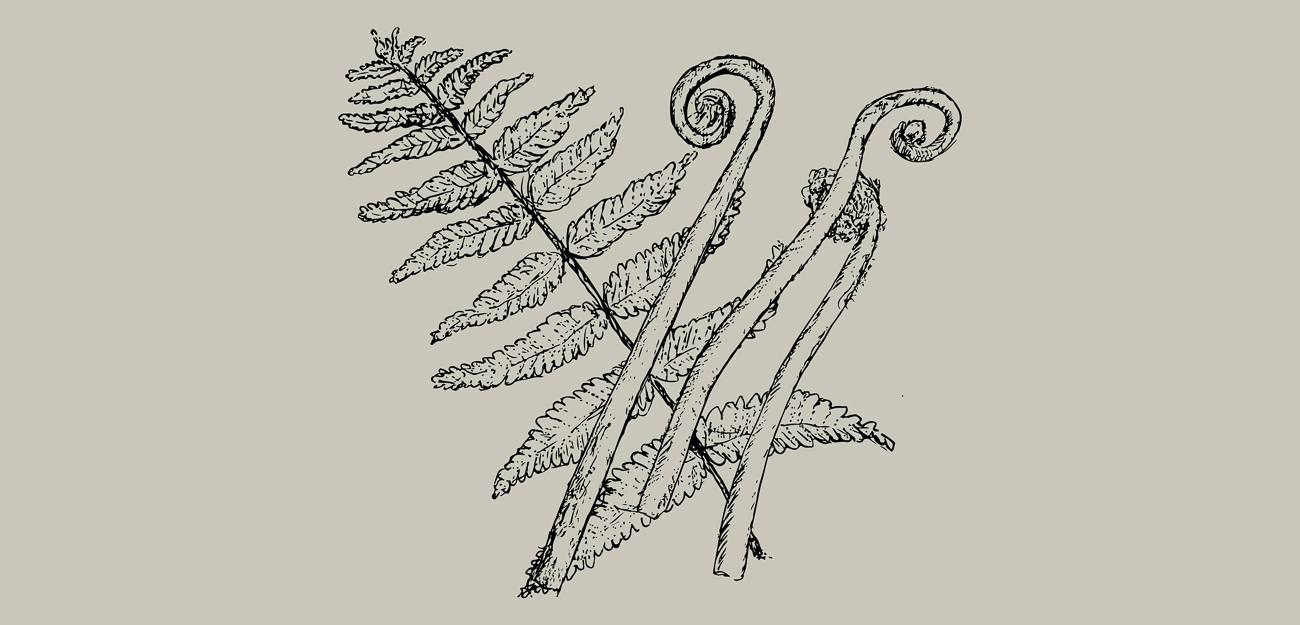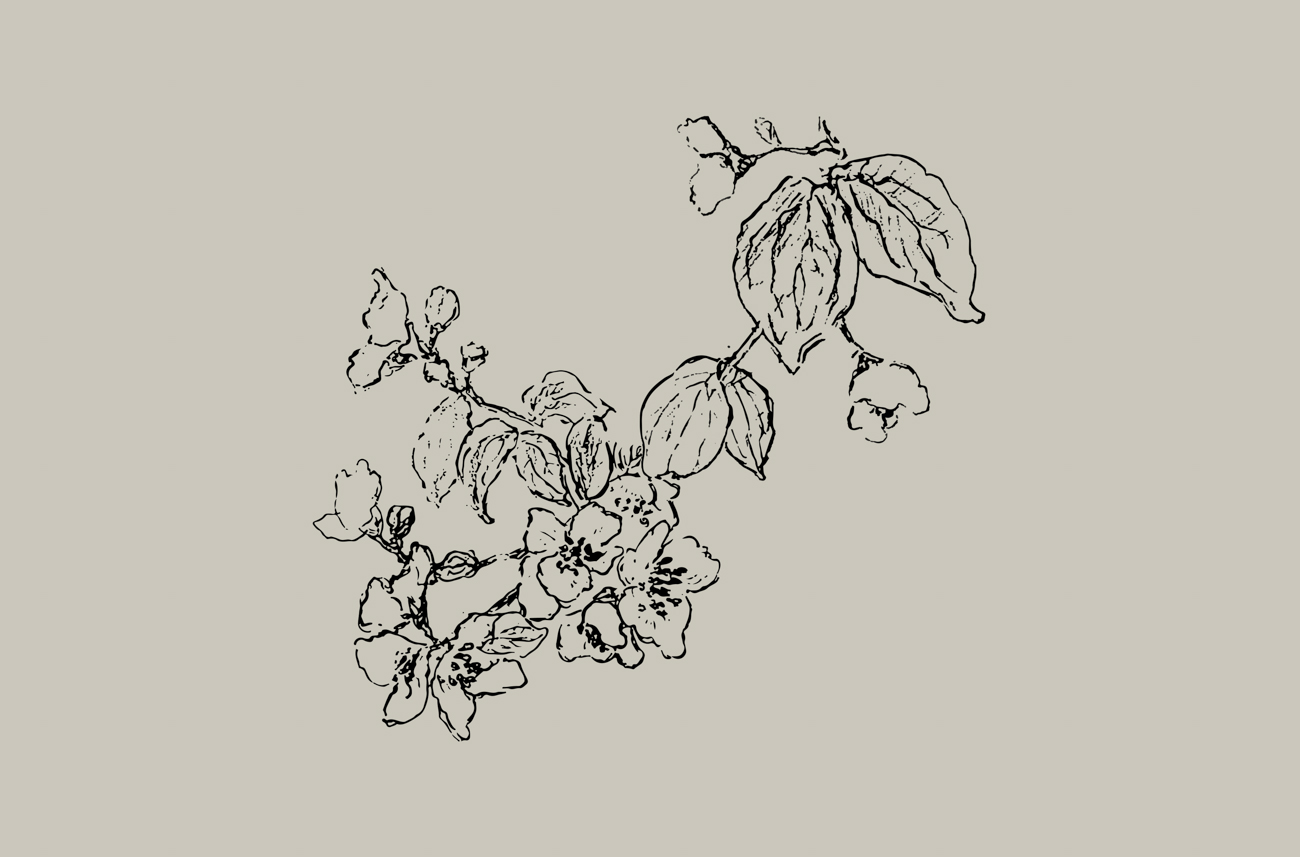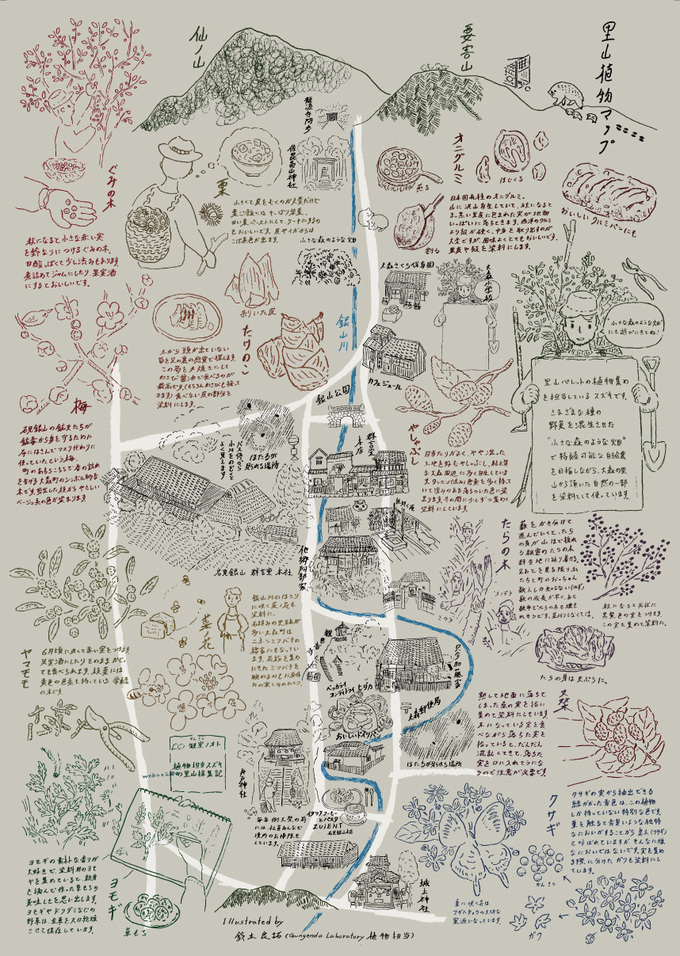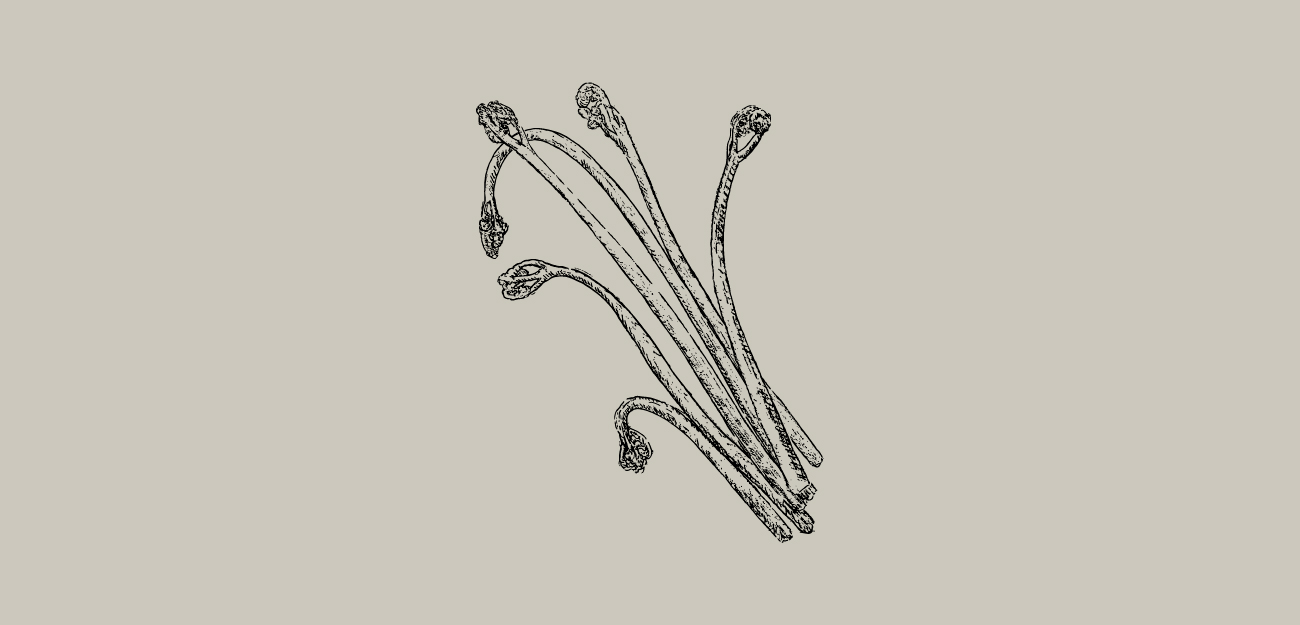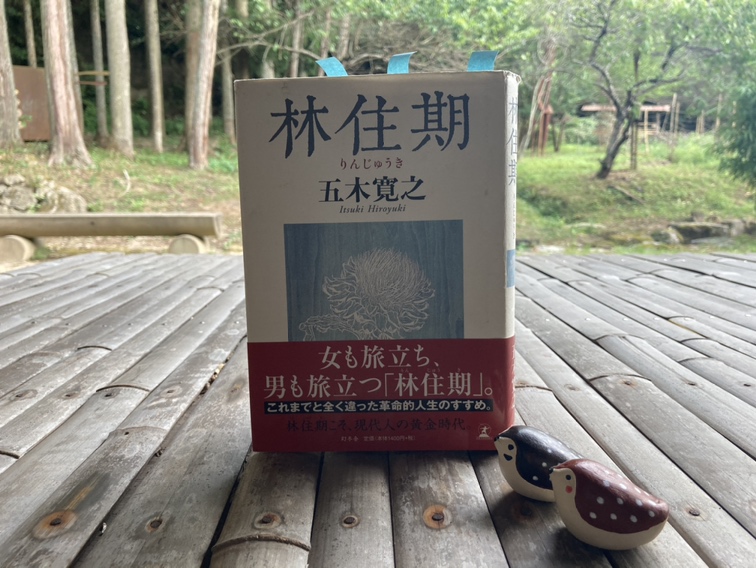群言堂から、
新しいお知らせです。
-
イベント情報
2月の期間限定イベント
-
イベント情報
期間限定イベント|B.stuff 革のバッグ展
-
お知らせ
【開催報告】中小企業庁主催「ローカル・ゼブラ調査事業 成果報告会」登壇
-
お知らせ
銀行保証付私募債の発行に関するお知らせ(石見銀山生活文化研究所)
-
店舗情報
移設・リニューアルオープン|〈石見銀山 群言堂〉仙台藤崎店
-
イベント情報
群言堂・松場忠登壇|オンライントークイベント『里山仕事ラボ』
-
メディア情報
『朝日新聞デジタル』掲載|松場登美「元気力㉒」
-
店舗情報
営業終了のお知らせ|〈石見銀山 群言堂〉堺タカシマヤ店
-
お知らせ
「ふくふく餅」をお求めいただいたお客様へお詫びとお願い(販売期間:2025年11月15日〜12月2日)
-
イベント情報
12月の期間限定イベント
-
イベント情報
11月の期間限定イベント
-
お知らせ
群言堂 会員様限定 「暮らす宿 他郷阿部家 2泊3日 冬の特別プラン(ポイント利用)」のご案内
-
イベント情報
10月のフェアのご案内|10%オフご優待/Wポイント
-
店舗情報
※復旧完了【お詫び】電話システムの障害について|群言堂/MeDuオンラインストア
-
メディア情報
『朝日新聞デジタル』掲載|松場登美「元気力㉑」
-
イベント情報
松場登美 出張イベント|ちくちくワークショップ&お茶会@城崎温泉
-
イベント情報
群言堂Instagram ライブ|「登美さんとお月見夜話」
-
イベント情報
10月の期間限定イベント
-
イベント情報
期間限定イベント|B.stuff 革のバッグ展
-
イベント情報
期間限定イベント|0401(わたぬき)のハコ 季節のストール展
-
イベント情報
期間限定イベント|tuduri―ツヅリ―物語の帽子展
-
メディア情報
Webサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」掲載|「遊ぶ広報」が目指す がんばらない観光地
-
イベント情報
丸井今井札幌店|オークヴィレッジ×群言堂 コラボチェア 受注会
-
お知らせ
ギフトショー出展|第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025
-
メディア情報
『朝日新聞デジタル』掲載|松場登美「元気力⑳」
-
メディア情報
Webメディア『ほぼ日の學校』出演
-
メディア情報
書籍『登美さん つくる、つくろう、私の人生』出版
-
イベント情報
d47 MUSEUM 島根物産MARKET|期間限定販売
-
イベント情報
6月の期間限定イベント
-
メディア情報
『朝日新聞デジタル』掲載|松場登美「元気力⑲」
-
メディア情報
『WWD JAPAN Weekly』掲載|石見銀山群言堂グループの取り組み紹介
-
メディア情報
雑誌『クロワッサン No. 1141』掲載|松場登美インタビュー
-
メディア情報
Webメディア『WWD JAPAN』掲載|石見銀山群言堂グループの取り組み紹介
-
メディア情報
Youtubeチャンネル『ほぼ日の學校』|対談動画配信
-
メディア情報
Webメディア『WWD JAPAN』掲載|スタッフ鈴木良拓インタビュー
-
メディア情報
Webメディア『WWD JAPAN』掲載|石見銀山群言堂グループの取り組み紹介
-
イベント情報
4月の期間限定イベント
-
店舗情報
4月16日(水)新店オープン|〈石見銀山 群言堂〉あべのハルカス近鉄店
-
メディア情報
『d design travel SHIMANE』掲載
-
メディア情報
Webメディア『ほぼ日の學校』出演